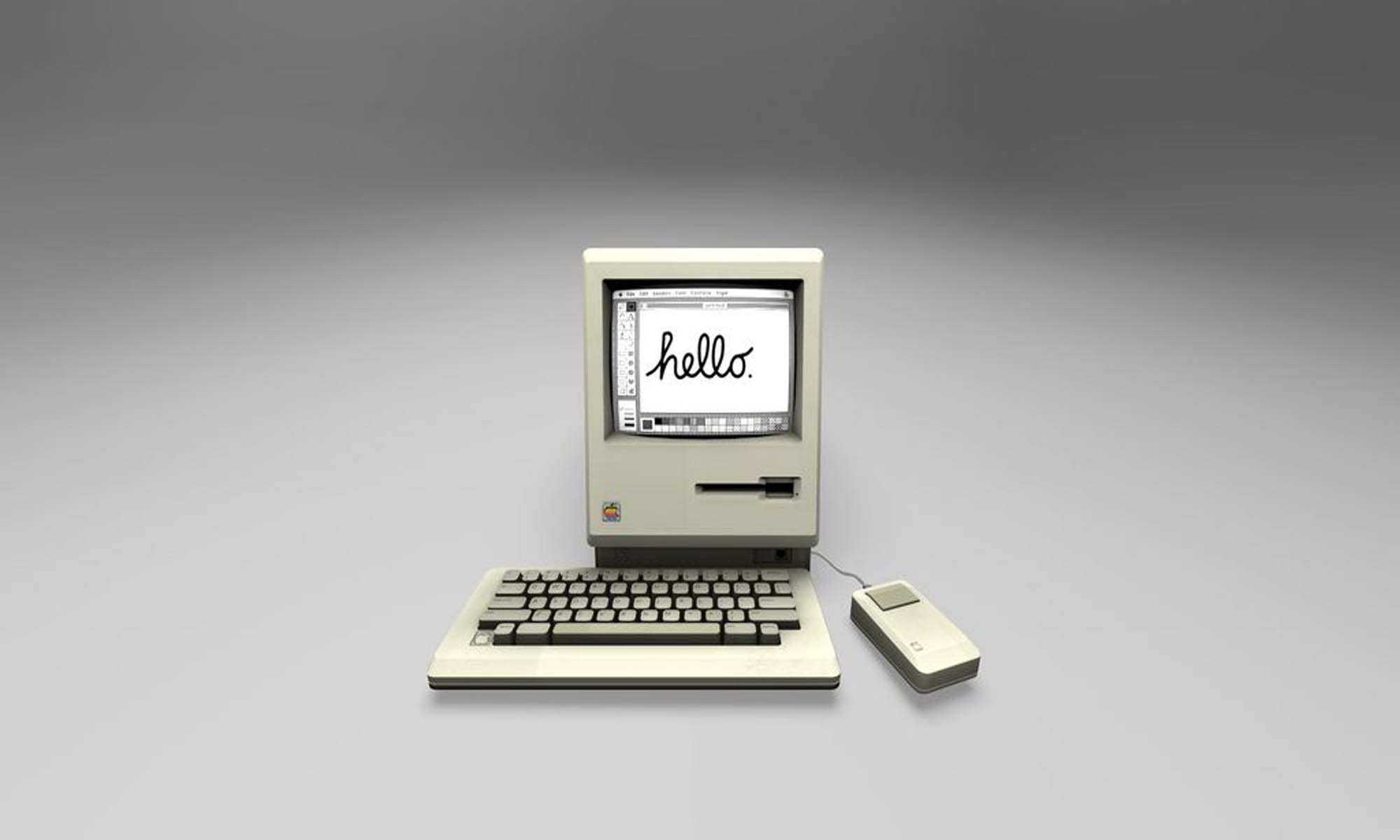瓶詰めが完了して、既に二週間がたちました。一週間目の味見では、やや酸味がありますが、ワインのようなフルーティな香りがする等の評価をいただきましたが、やはりまだまだ熟成が足りないような気がしました。
そこで、2回目の味見を実施いたしました。よく冷えた自家製ビールの栓を抜きますと、プシュッといい音を立てます。密閉度は問題が無いようです。グラスに注ぎますと、それなりに淡い茶色の泡が立ち、ホップの良い香りが立ちます。ここまでは、問題が無いようです。
そこで、味見ですが、気になっていたほのかな酸味が後ろに隠れ、苦みが前面に出てきました。また、淡い甘さもあり、ワインのような風味も感じます。ひょっとしたら、今までで、最もコクがあるかもです。とにかく、2杯目が飲みたくなりました。一応、成功のようです。

ところで、ビール造りで最も重要な要素のうちで、こだわりたいのが「水」です。ビールの90%を占めると言われていますから、味に直結するのもうなずけます。今回使用した水は、滋賀県湖西地方の比良山系から沢水です。地元では、金比羅の水と呼ばれ、金比羅神社の上方斜面から湧き出しています。味は、ほのかな甘みを感じる、いわゆる「軟水」と思われます。この付近の山が花崗岩地帯ですので、多分軟水でしょう。
ビール造りに適した水は、軟水か硬水かは、過去、ヨーロッパでも議論されてきました。当然、ビール造りを行う地方で手に入れやすい水を使うのが主流でしょうから、ヨーロッパは硬水によるビール造りが発達しました。
ミネラル量が少ない水は「軟水」と呼ばれ、スッキリとしてなめらかな味わいは、ピルスナーなど淡色系のビール造りに適しているといわれています。ちなみに日本でピルスナースタイルの淡色系ビールが主流となった要因のひとつに、日本の水は軟水が多いことがあるようです。
ミネラル量が多い水は「硬水」と呼ばれ、比較的味が濃く、ハッキリした飲み口になる傾向があることから、黒ビールなど味の濃い濃色系ビールに適しているといわれています。ヨーロッパでは、日本とは異なり硬水の地域が多いことから、現在でも濃色系ビールが盛んに造られているようです。今回、醸造したビールは、もちろん軟水で醸造したものですから、切れ味等で不利な面があるのですが、どうも、それは当たっているような気がします。味的には、切れ味というよりも、甘みのあるコクでしょうか。これは、個人の好みにも因りますので、今後の研究テーマかもしれません。
その3に続く